|
3 老人文学としての辻井喬の小説ーーー辻井喬『終わりからの旅』『虹の岬』『父の肖像』
『虹の岬』は、はやふた昔にもなるだろうが、三国連太郎主演の映画を見てすませた。
映画より前、鹿児島を歩いた折にはこの小説のモデル川田順の歌碑を2つ(佐多岬=展望台下・野間岬=ロラン局の先)訪ねたこともあったが、川田に独特に美化された「天皇」観があることはこの本で分かった。
短歌では現在川田の歌がどのていど読み継がれているのかがよくわからないし、ボクも断片的に、山を詠んだものなど何十首かを読んだことがあるはずだ、と思う程度だが、往年は歌壇の有力歌人の一人であった。
が、今はゴシップ「老いらくの恋」あたりが面白がられているようで川田には気の毒なことだ。
辻井がなんで川田をモデル小説に使ったのか、ということでは天皇論にからんでいるらしい(映画ではこのことはよく分からず、代わりに、住友を他の財閥のように戦争に深入りさせずに守った功績を最後に印象付けている)のであるが、手短に書きづらいので割愛。
いま読んでみての感想 2014/12/19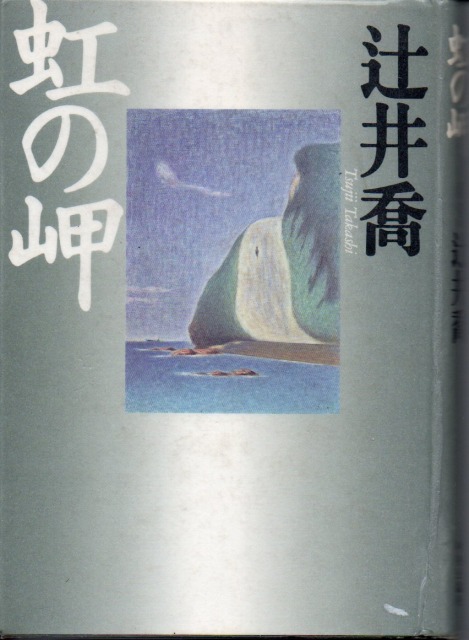 『虹の岬』中央公論社
1994発行 『虹の岬』中央公論社
1994発行
とうとう読んだのであった! 就眠前の少しばかりの時間を、数夜をかけて。今は中公文庫にもあるようで、そのほうが寝床で読むのには楽であったが、偶然、地元図書館で目にとまり、単行本を借り出した。
一番の印象は「映画はこの本の物語を相当に組み立て直していたのだ」ということ。
三國連太郎・原田美枝子が主演した映画は、純愛・不倫の物語として映像も美しく描かれているが、原作を読むと、川田順の住友での存在の仕方=職業観が繰り返し叙述されており、作者自身(堤清二)の企業経営者としての矜恃がどのあたりにあるのかを、問わず語りに語るものとなっている。
また、軍部主導の統制経済への反発と住友退社の経緯は、それほど仔細ではない。
歌人としての川田順については、一応の評論にはなっているが、記述が散漫で通り一遍の印象が残る。作風の変遷が概念的な大づかみさを抜けておらず、それぞれの局面をよく表す短歌の例示がもっとあってこそ、「戦後」という一時代を代表し、かつ、今は忘れられつつある歌人の実像を伝えることのできる評伝になったのではないだろうか。
ということは、「小説家・辻井喬」のこの一作の眼目は、企業人と文学者(主には短歌)という二足の草鞋をはいて両立を成し遂げた先達への敬意がひとつ。
もう一つは、人間の愛欲という業への省察。これは近代文学の最大テーマであるだろう。ここにも作者=私人「辻井喬」の立場からの、心寄せるに値するほどの女性像のスケッチがなされ、当然にも、それと対になる男性のあるべき形の提示にもなっている。
社会制度的(キリスト教的倫理規範)枠組から逸脱しながらでも、一度限りの命を生ききろうとする人間のエロスを肯定しておきたい、という衝動を、伝記小説という器を使って表現しようとしている。従って短歌作品への考察を主軸とした「歌人・川田順」の評伝では全くない。むしろ本物の企業人のあるべき姿として、川田順への敬愛がこの一作を書かせた、とでも言う方が正鵠をえているのかもしれない。
鈴木斌氏が『老人文学論』中に指摘している「川田に独特に美化された「天皇」観があること」の部分は、今回の読書で了解できた。川田は現在の天皇には戦後間もない少年期(皇太子)に、短歌の手ほどきを行い、彼はその不倫事件でその任を五島茂に代わり離れた。この役割において祖父は明治天皇に仕え、家系への誇りと、敗戦による失意を深めていたのであった。
川田の歌柄の大きな叙景歌は、かつては広く認められるところであったし、その景が詠まれた土地の多くに歌碑が建立されもしたが、今日、川田順の名や歌が膾炙されることは希である。
ちなみに手元の数冊(*下記4冊)を書架から引き抜くと、はじめ三冊において川田の作品の収録は確認できなかった。あとの二冊には載る。
講談社学術文庫 『高野公彦編・現代の短歌』1991発行
国文社 現代歌人文庫 目録(第一期30巻・第二期既刊7巻)
本阿弥書店 『現代短歌をよみとく』岩田正 全30章対象歌人 2002発行
本阿弥書店 『昭和短歌の精神史』三枝昂之 2005発行 この本では評論の対象歌が散見できる。
小学館『集成・昭和の短歌』岡井隆【編】 1995発行
この本では窪田空穂、会津八一に続く3人目として百首ほどが載る。(伊藤一彦選)
より多くに当たるいとまがとれないので以上としておくが、今日的時代気分において、人口に膾炙するには馴染みやすい歌が無いのかもしれない。ボク個人は彼の叙景歌何首かは好ましく感じてきたのであるが、、、もう思い出せないなあ、遠路わざわざ訪ねていった鹿児島の野間岬と佐多岬に建っている大きな歌碑に彫られた歌を。
川田順の短歌鑑賞 2014/12/28
小学館『集成・昭和の短歌』岡井隆【編】 川田順は伊藤一彦が選出、中より
『鷲』 (s15刊)
劔岳深碧空ふかあおぞらに衝き峙たちてあな荒々し岩に痩せたり
高やまのいただきにして真夏日は上汚うわよごれせる堅雪かたゆき照らす
立山が後立山に影うつす夕日の時の大きしづかさ
山空をひとすぢに行く大鷲の翼の張りの澄みも澄みたる
大鷲の下おりかくろひしむかつやま竜王岳は弥いや高く見ゆ
寄る浪の飛沫しぶきの搏うてば鴨鳥の或は啼きて岩すりて飛ぶ
国のため戦争いくさに出づるますらをの親は人混みにもまれて行きぬ
じつと考へ額ひたひに汗が流れきぬ日露戦争よりも大きくならむ
少年団の喇叭の声は整はず汗をたらして吹きつつ行けり
この駅を今発たつ兵の顔見れば皆吾児あこよりも若きが如し
長篠のいくさの日にもこの部落むらは夏蚕なつこ養かひけむ今日のごとくに
相変わらず鎗刀やりかたなにて勝つものと弾丸たまへ飛び込みし甲斐の勢せいはや
智略乏しく滅びし者の跡に佇たてり汗ふきながら憤いきどほろしも
* 戦後、川田は戦争賛美を詠んだ歌人の一人という言われ方をしたが、上掲7首目以後の7首を詠むと、戦争協力者としての十把一絡げは間違いのように思う。第7首目などは木下恵介『陸軍』中のクライマックスシーン、すなわち見送りの群衆に阻まれながら懸命に息子を捜して走る母親の姿に重なる。
『東帰』 (s27刊)
樫の実のひとり者にて終らむと思へるときに君あらはれぬ
夏山の夜よるの青さに見惚れ居りそのふもとには君が家あり
山家集に一首すぐれし恋のうた君に見せむと栞しをりを挿む
相触れて帰りきたりし日のまひる天の怒りの春雷ふるふ
事なしに生きむと願ふここにさへ世の人言ひとごとはなほも追ひ来る
『父の肖像』は出た当時読んだ覚えがあるが、堤一族物語としては虚実交えたものを読んでも始まらないような、作りすぎた感じがした。
けれども、彼には己の
出生への深いわだかまりがあって、今もなお一族への反発心や、自分探しの旅を続ける(全く比喩でなしに)理由になっている。本書は冒頭、父親の郷里の一員には混じりたくないことを夢中独白の調子で語り出す。
以下、同じく冒頭部分、自分が中学(旧制)三年の時のこと、父のことばである。
「世間にはわしの事を不身持のように言う奴がいるが、お祖父さんから預かった楠の家を守っていくのは並大抵のことではなかった。お前も大人になれば分る」
かれは少年時代にあったこのことを、
その「不身持という(父の)ことばが私には分らなかったのである」といったんは書く。
そして「それが、、、分かったのは大学へ行くようになってからだ。そうして、その意味が分った とき、私は父が嘘を吐いたのだと直感した。」 とき、私は父が嘘を吐いたのだと直感した。」
また、戦争と天皇制が本作の基底部に置かれていると鈴木氏が指摘するが、あらかじめそういうことに十分注意を払って読み進めば、作中主人公の唐突な決意も、心情的にはわかるのかもしれない。実人生の不本意(セゾングループの破綻)は全部ガラガラポンで放り出したい衝動を伴うものであったかもしれない。
若いときに彼が共産党員であった(これについても「父親への反発心が大きくはたらき、、、」と語る)ことが、時代を風俗表現する方便としてではなく、彼の思考回路に今も大きな影響を残していることは、この本を読めばあきらかであろう。 講談社 2004/9/30発行
- 再読しての感想 2012/02/29
鈴木氏が書かれたことを念頭に置いて読んだわけだが、やはり、天皇制のことは文脈においては薄いと思う。父(文中=橘治郎・本名=堤康次郎つつみ やすじろう)は保守二党合同(=55年体制・これによって自由民主党が誕生)の力学から少数派におりながら衆院議長に就いた。このとき、天皇に挨拶するための参内に際して戸籍にない実質上の妻を伴ったことがゴシップ沙汰になりかける失態があった。彼にとっては生涯にわたってやまなかった放埒な女性関係の中での小さな躓きにすぎず、作中でも父には「とりつくろい」だけが必要であったようすが書かれている。
正妻(作者=恭次の育ての親)からは、戦前、夫が斉藤隆夫が「粛軍演説」や「大陸政策批判」を行った等のことから議員除名となった際、節を曲げて斎藤除名に賛成票を投じたことや、続いて翼賛議員となって保身に動いたことに反感を持たれ(著者の見方)、長く別居中になっていたのであった。
この「愛人問題」もみ消しにひと働きしたのが作者であった。しかしこのあたりを含め通読してみて、天皇制に醒めた見方はもっていても、強い葛藤を感じさせる場面はなかったように思う。(作者の本心や、やっかいごとを書かない知恵の有無はわからない)
やはり、共産党活動家の体験(これは天皇制の裏返しのやっかいごとであるだろう)は、作者にとって、もう一方の物差しとして生涯を規定してきたらしいことを窺わせる既述が随所にみられる。彼がある種の倫理観を企業経営者になってからも捨てきれなかったことが、あるいはその若き日の真剣で貴重な体験が彼の矜恃であったことが、率直な記述として随所に見られる。若いときから詩を書いてきたり、車谷長吉が世に出るまでのある期間をセゾン本部に抱え養ったような事実が自ずと想起されよう。
さて、私小説の宿命、書かれた側がこの作品中のモデルとして一役買わされていることを嬉しく思うのかどうか、、、。僕の勝手な推測では、書かれたことを、文芸というものへの余程の理解者以外は全く喜ばなかったに違いない。
本人(辻井)が自分のことも十分客観視しつつ、身辺の人間をいくら公平に書いたつもりであっても、父以外の者へも相当に辛辣であり、書かれた側は「あることないこと勝手に書きやがって」と感じるに違いない。身辺実在、特に生存中の人物を書いてしまうことには私小説タイプの作家の「大変さ」というものを感じる。
最後に、作者が父を、本当はどう思っていたのか。
表のアナウンスとしては父親への反発が色濃い。その一つは自分の出生の謎のことがあるだろう。
本人にも周辺にも早逝した父の弟夫婦の子と説明されていた。それを否定できる具体的なモノがあるわけではないものの、本当の父とは叔父ではなく今の父そのものではないのか?
また、実母も叔母ではなく、表には出せない若い女性に産ませた子であった(かもしれない)という疑いがあった。
加えて、横暴な家父長としての一族支配の理不尽さ、ということも事実であり実感であるだろう。
しかしそれは本当にそうなのか。
作者は、父が衆院議長に就任したことがきっかけで秘書として協力するようになって以来、曲折を経てコンツェルンの一翼を任されるようになり(兄弟中で一番父の信任を得た)、実は深いところで父を敬愛してやまなかったのではないだろうか。
そもそも、嫌いな者の像を手間暇かけて、おのれひと世の名残として描ききるだろうか? 彼はこの長編を書くことを通じて改めて育ての父(実父かもしれない)への思いがどの程度かには改まったのではなかったのか。
作品としては、余分の重複など気になるところもあるし、前半が無味乾燥(歴史テキストのような)のきらいもあるが、半ばにきて作者が成長してからの、自身の記憶に基づくディテールが増すににつれて読み物として面白さが出てくる。
本人、堤清二は1927年生まれ、著述期間は不明だが早くから資料収集の準備があったと思われる。単行本に先駆けて某文芸誌に連載された上で2004年に初版が出た。この年76歳だったと思われ、十分老人文学であると言えよう。
| ![]() ←目次に戻ります
←目次に戻ります![]() ←目次に戻ります
←目次に戻ります